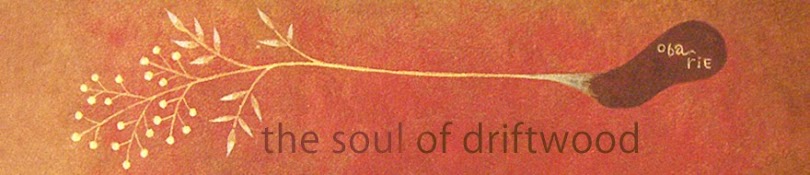16 11月, 2018
久住山へ
大分県の山、久住山(1786.5m)に30年ぶりくらいに登った。
前日、ひとり高速を飛ばしてきた疲れか、単独登山の緊張か、登山当日の朝、軽い頭痛と軽い吐き気があった。一瞬、登山やめて部屋で寝てようかとも思ったが、ホテルにお弁当頼んでいたから、とりあえず受け取りに行き、ロビーまで下りたら、せっかくだから車で登山口までは行ってみようと思い直し、一応用意した装備を持って出かけた。
空は晴れていたが、登山口の駐車場で車を降りたら風が冷たい!
シャツ、セーター、ダウン、ヤッケと全部着込んで、とりあえず行けるところまで行って、体調と相談しながら歩くことにした。
頭は重いのに、意外に足は動く。普段、体調良くても、息はすぐ切れ足は重くなるのに。不思議だった。
引き返す距離も頭に入れて、これ以上無理と感じたら引き返すつもりで、様子みながら歩いたら、標準タイムよりは30分遅れの3時間ほどで久住山頂に到着。
写真では、石ころしかない山に見えるが、登山口から山頂までの間には、箱庭みたいな場所もあり、岩場ありハシゴあり、高山植物もあり、でバリエーション豊かな山だと思う。
山頂まであと10分くらいあたりで、下ってくる人とすれ違うとき、「山頂、もうすぐですよ」と声かけてもらい、嬉しかった。登山口で「すごく寒いですねー」と声かけてくれた人だった、と思う。声が似ていたから。
ほとんど下向いて登ってるから、顔はほとんど見てないさ〜。
山頂からは、阿蘇の五岳の仏陀の涅槃像もキレイに見えた。
いろんな人がいた。女性一人で登ってる人は他にも何人か居た。
犬を連れて登ってる女性もいた。犬が相棒っていいな。
大人でもしないような真剣な表情で必死に先生について歩く幼稚園児たちのグループにも会った。愛おしかった。その一人一人を写真に撮って、彼らが20年後30年後に壁にぶち当たったとき、見せてあげたいと思ったくらいだ。
2年後のスペイン巡礼の旅の練習のつもりで登ったが、気候に対する装備など、今後の課題もわかり、よい山行だった。
10 11月, 2018
映画「ゲッベルスと私」
〜キネマ大羽〜 今年の「見て考えるのじゃ」の一本
時折差し挟まれるナチス関連のアーカイブ映像以外は、第二次世界大戦中ドイツの宣伝相ゲッベルスの秘書として働いていた、102歳のブルンヒルデさんが独白する上半身が、画面いっぱいに映し出されるのみのフィルムだ。
ドイツ語がわからない私には、日本語字幕を読む作業に徹するような鑑賞形態となり、まるで読書をしているような気分になった。
彼女は、たまに感情を表すことはあるが、年齢からはとても考えられないほどの明晰さを発揮しながら、始終淡々と記憶を語る。
私は(ホロコーストを)知らなかった。私は悪くない。という、彼女の発言に見る者の心はわずかにざわつく。
だが、しかし、あなたならどうするか?私ならどうするか?
と考えてみると、ブルンヒルデさんをジャッジできる資格はないだろうな、と思い直す。
途中、何度か眠くなったので、大切なメッセージを見逃したかと思い、めずらしくパンフレットを購入した。
とくに見逃した重要なメッセージはなさそうだったが、パンフレットの最後のページに、小さめの字で、〜映画で伝えられていないこと〜という囲みを見つけた。
映画で語っていたブルンヒルデさんには、1936年当時、半ユダヤ人の恋人がいた、というのだ。
その恋人は、迫害から逃れるためにひとりオランダに亡命し、その頃、彼女は彼の子を身ごもっていたが、肺を悪くしていたため医者に勧められ、中絶をしたという。
そして、何回かオランダで密会していたが、当局から怪しまれることを恐れて密会をやめ、戦争勃発を機に音信不通となった。
と書いてあった。
そういう彼女の個人的背景を知ると、彼女の口から語られた内容からくる印象が、また違ったものに感じられてきた。
ただ、映画の中で、あえて監督が上記の事実を一切伝えなかったのは、「ゲッベルスと私」の私とは、ブルンヒルデさんだけのことではなく、もしも、私がナチスと関わることがあればどうするか、ゲッベルスの部下だったらどうするか、彼女と同じ立場にあるとしたら私はどうするか?、というところに焦点を当てて考えてほしいから、という監督の意図があったから、ということらしい。
最近の映画パンフレットは、値段の価値も無いようなのが多いけど、今回は、パンフレット買って良かった、と素直に思った。
そして、映画が眠かろうが、反発を感じようが、兎にも角にも、私たちは映画のテーマについて自分の頭で考えなければならないのだ。
余談だが、当時日本の有名女優と宣伝相ゲッベルスが一緒に写った写真が残っている。
原節子だ。1937年の日独合作映画でデビューして間もない美しい原節子とゲッベルスが並んでいる写真を見たとき、歴史に翻弄され背負うものもあったのだろうな、と、ふと思った、
登録:
投稿 (Atom)